はじめに
こんにちは。
りこぴんです。
みなさま、ChatGPTによる通知表所見の作成に、興味はありますか?
所見の作成は、教師にとって大仕事のひとつですよね。

興味はあるけど、ほんとにできるの?



AIなんかに大事な所見を書かせていいの?
と思われる方が多いのではないでしょうか。
ご安心ください。
ほんとにできるし、書かせても大丈夫。
今回の記事では、
ChatGPTを活用した、通知表所見の作成法
を紹介したいと思います。



まだまだ私も手探り段階ですが、興味がある方は、ぜひ最後までご覧くださいね。
実際のやり方・手順をご紹介します。
鍵は、プロンプト
まず結論から。
ChatGPTに所見を書かせるには、以下の情報・条件を与えるとよさそうです。
- おおまかな文字数
- 構成
- 定型文や、使って欲しい言い回し
- 対象学年、年齢等
- 内容(だいたいでいい)



箇条書きで条件を与えれば、おおむね書きたい文になります。
たとえば小学1年生に向けた形で作成するとしましょう。
以下のようなプロンプト(命令文)を与えてみました。
通知表の所見を作成してください。
条件は以下の通り。
・250字程度。
・2部構成。1部目は教科、2部目は生活面。
・1部目は、「◯◯科『◯◯』では、〜することができました」という言い回しから始める。
・2部目は、「係活動では、◯◯係として、〜することができました」という言い回しから始める。
・文自体は、4文程度。
・小学校1年生
・国語科のおおきなかぶ
・黒板消し係
をがんばった児童でお願いします。
ポイントは、わりと細かく条件を指定しているところです。
その結果、提案された文がこちら。
国語科「おおきなかぶ」では、登場人物の気持ちを考えながら音読することができました。セリフの強弱や声の大きさを工夫し、聞いている人に気持ちが伝わるように読む姿が見られました。友達と一緒に場面を分けて読み合う活動にも意欲的に取り組み、物語の内容をしっかりと理解できました。
係活動では、黒板消し係として、授業の合間に進んで黒板をきれいにすることができました。毎日責任をもって係の仕事を続け、教室を気持ちよく使えるように工夫する姿が立派でした。
うん。悪くないのでは。
すでになんとなく、それっぽくまとめてくれています。
ただこのままではちょっと抽象的で、無機質。



当たり前ですね。ざっとした情報しか与えていませんから。
そこで、情報を追加することにします。
たとえば、続けて次のようなプロンプト(命令文)を与えてみましょう。
条件を追加します。
・おおきなかぶでは、「うんとこしょ、どっこいしょ」の読み方をがんばったこと
・黒板消しの仕事では、ときに友達と消す順番でもめることがあったこと
後者は、保護者も児童も不快にならないやんわりとしたニュアンスでまとめてください。
より具体的な情報を加え、あえて所見に書くことは推奨されない「マイナス面の姿」も要望してみました。
その結果はこちら。
国語科「おおきなかぶ」では、「うんとこしょ、どっこいしょ」のかけ声を元気よく、気持ちをこめて読むことができました。声の大きさや間の取り方を工夫し、聞いている人に楽しい雰囲気が伝わるように取り組む姿が見られました。友達と一緒に役割を分けて音読する活動でも、意欲的に参加し物語の楽しさを味わうことができました。
係活動では、黒板消し係として、授業の合間に進んで黒板をきれいにすることができました。ときには友達と順番を相談する場面もありましたが、話し合いながら協力して取り組もうとする姿勢が育ってきました。
どうでしょうか。
わりと使えるレベルの文になったのでは?
だいぶ具体化された印象です。



「もめる→相談する」の言い換えは賛否両論ある気はしますが(笑)
やはり、鍵はプロンプトです。
所見文は、ある程度の定型文があったり、自分が書き慣れた文体があったりすることでしょう。
そこをはっきり「条件」として指示すれば、おおよそ自分が書こうとしている文に仕上げてくれると思います。



納得いかなかったり、管理職からの指示があったりした場合は、またさらにプロンプト(命令文)を追加すればよいのでは。
おすすめは、ベースを固め、一気につくってしまうこと
実際にChatGPTを活用して所見を作成する場合は、ベースの書き方を決めて、一気につくってしまうのがよさそうです。
具体的にシミュレーションしてみましょう。
以下は、先ほどつくらせた例文です。
国語科「おおきなかぶ」では、「うんとこしょ、どっこいしょ」のかけ声を元気よく、気持ちをこめて読むことができました。声の大きさや間の取り方を工夫し、聞いている人に楽しい雰囲気が伝わるように取り組む姿が見られました。友達と一緒に役割を分けて音読する活動でも、意欲的に参加し物語の楽しさを味わうことができました。
係活動では、黒板消し係として、授業の合間に進んで黒板をきれいにすることができました。ときには友達と順番を相談する場面もありましたが、話し合いながら協力して取り組もうとする姿勢が育ってきました。



うん、このレベルなら使っていいかな!
と判断した場合。
次からは、これをベースに、ちょこちょこ条件を変えていけばいいです。
たとえば、続けて以下のプロンプト(命令文)を与えてみます。
この例文をもとに、
・「まだまだかぶは、ぬけません」を友達と協力して読んだ
・配り係(おてがみ配布)を素早くやった
パターンをお願いします。
すると、結果はこちら。
国語科「おおきなかぶ」では、「まだまだかぶは、ぬけません」の場面を友達と声をそろえて元気に読むことができました。セリフに気持ちをこめ、楽しい雰囲気が伝わるように声の大きさや間の取り方を工夫していました。友達と役割を決めて読み合う活動にも意欲的に参加し、物語の面白さを味わうことができました。
係活動では、配り係として、おてがみを素早く丁寧に配ることができました。周りの友達の様子を見ながら進んで取り組む姿から、係の仕事に責任をもって行動しようとする気持ちが伝わってきました。
うん、これも悪くない気がします。



個人的に引っかかる文はありますが、まあ手直しすればいいかなと。
この調子で、少しずつ書きたい子どもの具体的姿をイメージして伝えていけば、バリュエーション豊かに作成できるんじゃないかと思います。
ベースをしっかりつくっておけば、どんな内容でも、それなりの完成度になりそうです。
ちなみに私の場合、ベースの例文を作成するのに使った時間は4〜5分。
内容をマイナーチェンジさせてつくった、2つめの例文に至っては、数十秒です。



普通にイチから考えるより、時間短縮になるのは間違いないと思います。
あとは完成したぶんから、Excelにでも貼り付けていけばいいのでは?
ChatGPTで所見文をつくるのは、けっして悪くない
このように、AIを活用しても、それなりの所見を書くことはできそうです。
しかしそれでも、



だいじな子どもへの所見でしょ?
AIになんか任せちゃだめじゃない?
って感じる先生は多いのではないでしょうか。
わかります。
手を抜いちゃってる気がするんですよね。
とはいえ手順をご覧いただいたなら分かると思いますが、
内容を考えているのは、まぎれもなく、先生自身です。
ChatGPTは、先生が書きたいと思う内容を、わかりやすくまとめる手伝いをしてくれただけ。
なんなら、
- 書きつかれて訳のわからない文になる
- 誤字脱字だらけの文になる
よりも、よっぽど保護者や児童に配慮してるのではないかと思います。



あ、チェックする管理職の先生たちにも、ですね(笑)
手を抜いているわけでは、まったくもってありません。
そこはご安心いただいていいのではないでしょうか。
AIを活用する仕事術のすべてに言えることだと思います。
おわりに
通知表の所見作成は、教師にとって大仕事のひとつ。
この作業をうまいこと効率化できれば、負担感はかなり減るのではないでしょうか。
繰り返しますが、べつにAIを使って書いたからって、手を抜いてるわけではありません。



作成のスピードが上がり、なおかつ読みやすい文になるのなら、使えるもんは使ったほうがいい!と個人的には思います。
もちろん、保護者や子どもに「これAIが書いてますから〜」なんてわざわざ言うメリットはないと思いますけどね(笑)
興味をもたれた方は、ぜひ試してみては?
ただ、私もまだまだ試している段階なので、もっといいやり方やプロンプトがあるかもしれません。
ご了承を!
ではまた!

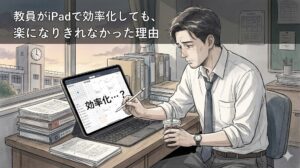
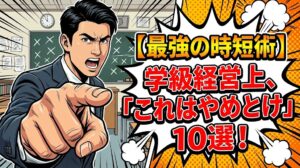






コメント